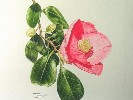暮らしの学校 - 講座詳細
初めての方にも解りやすい
歌舞伎の楽しみ
講座番号:254-474

講師:丹羽 敬忠
講座内容
歌舞伎の基本について、初めての方にもわかりやすく、詳しく解説してゆきます。また、名古屋で歌舞伎が上演される時には、その演目の見どころなども楽しくお話していきます。
講座詳細
開催校
岡崎校
回数
6 回
開講日
01/19(月)、01/26(月)、02/09(月)、02/16(月)、03/09(月)、03/23(月)
時間
10:00 ~ 11:30
受講料
10,890円 (税込) [6回分]
持ち物
筆記用具
教材費
プリント資料代別(500円程度)
備考
お車でお越しの方は第3駐車場のご利用が便利です。★1/19と2/16は教室が第1教室になります。
講座カリキュラム
1回目
01/19(月)
第1教室
①双蝶々曲輪日記(ふたつちょうちょうくるわにっき)
「忠臣蔵」「菅原」「千本桜」の名作を出した作者トリオが「夏祭」の好評に引き続いて、世に送った上方の世話物浄瑠璃である。
2回目
01/26(月)
階段教室
②双蝶々曲輪日記(ふたつちょうちょうくるわにっき)
人形浄瑠璃から歌舞伎に移入されて人気が出た演目である。前髪の角力取り、町家の若旦那、廊の遊女を中心に父親・母親・嫁といった家族を登場させ、彼らがそれぞれの立場で義理と人情の相剋に悩みつつ生きていく姿を描いて、その世話物の特徴をよく出した作品である。
3回目
02/09(月)
階段教室
③双蝶々曲輪日記(ふたつちょうちょうくるわにっき)
歌舞伎では天保初年頃までは通しに近い形で上演されていたが「角力場」「米屋」の上演が多くなり、時に「橋本」「道行」が加わることがあった。
4回目
02/16(月)
第1教室
④双蝶々曲輪日記(ふたつちょうちょうくるわにっき)
「引窓」は幕末以降上演が途絶えていたが、明治になって中村雁治郎が復活、当たり狂言となった。以後歌舞伎の人気演目となっている。
5回目
03/09(月)
階段教室
⑤双蝶々曲輪日記(ふたつちょうちょうくるわにっき)
6回目
03/23(月)
階段教室
⑥双蝶々曲輪日記(ふたつちょうちょうくるわにっき)